第139話 ■バクダン屋
- 1999.11.08
- コラム
実家の2階の窓から見える、小さなお稲荷さんの隣は物心ついたときから長い間空き地であった。いつの間にかそこに家が建ってしまったが、それまではこま遊びの会場として使用させて貰った。そう言えばここに一度だけ「バクダン」屋が現れたことがある。バクダン屋を見たのは後にも先にもこの一度きりだ。バクダン屋とは何とも物騒な名前であるが、バクダン菓子をその場で作ってくれる親爺のことである。バクダン菓子とは言うならば米のポップコーンのことで、「ポン菓子」と呼ばれていたりする。駄菓子屋では今でも赤い三角形のビニール袋でニンジンのような姿で売られている。何故これがバクダン菓子かはその製造過程を見れば一目瞭然だ。
昭和50年頃だったと思うが、その親爺は自転車にリヤカーを引いて現れた。リヤカーには大きな金網とボンベが乗っている。子供達がバクダン屋を見るのは初めてのため、変なリヤカーを引いて現れた、このおじさんがこれから何をやるのかは不思議でしょうがない。客寄せも含めて親爺は早速デモを始めた。圧力釜に手の平一杯ぐらいの米を入れ、それをボンベの火で加熱しながら回転させる。しばらくすると(この「しばらく」がどれぐらいかは記憶していない。子供心には長い時間の様だった気がする)火を止め、金網に向けて圧力釜の蓋を開けたとたんに大きな「バン」という音と白い煙を出し、バクダン菓子が金網向けて飛び出した。そのうるさいこと、うるさいこと。なるほど、バクダン菓子である。音とともにまた人が集まり、大人達は懐かしそうにそれを見ていた。
少々の米と味付けのための砂糖、それに手間賃の100円を持ってくればバクダン菓子を作ってくれることが分かると、これらを調達するために家に戻る子供もいた。もちろん自分もその一人である。大きなビニールのゴミ袋(もちろん未使用)に入れてもらった出来立てのバクダン菓子はとてもうまかったが、全部食べるのには難儀した。
-
前の記事
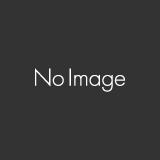
第138話 ■リベロ 1999.11.05
-
次の記事
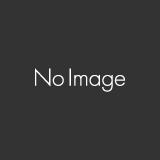
第140話 ■忍者 1999.11.09