第560話 ■片思いの美学(5)
~ 気づかない女
このままずっと、この店で暇を潰しているわけにはいかない。
わざと時計を見て、次のアクションへのサインを送ってみた。
「どうしたの、時間なんか気にして?。何か用があるの?」
「ううん、別に。用はないけど、そろそろ眠くなってきたなあ、なんて」。
「私も酔っぱらって、ちょっと眠くなって来ちゃった」。
「じゃあ、そろそろ、ここ出ようか?」。
「何?、今日はこれでバイバイ?」。
「いや、もっと静かな所へ行こう」。
しばし、お互い黙り込む。
「やーだ、秀野君、Hなこと考えているでしょう?」。
私は片手に会計伝票、そしてもう一方の手で彼女の手を握ったまま、動きが止まった。
途端に彼女が笑い出す。
「私ねー、ダメなんだ。相手も自分のこと好きなんだなあ、って分かった瞬間に冷めてしまうの。最初、私の方から好きになって、けどお互いの気持ちが通じ合った途端に何だかドキドキ感がなくなってしまって。片思いってさー、究極の恋愛のスタイルだと思うんだ。現実が理想を上回ることなんか有り得ないし。100から始まってあとはそのポイントが減って行くばかりだから。と言っても最近は100から始まることもないけど。結局私には片思いがお似合いみたい」。
彼女のドキドキ感があろうとなかろうと、今私の心臓は大きく鼓動している。
「確かに私は秀野君のこと好きだったし、今はもっと好きかもしれない。けど、こうして二人っきりでお酒が飲めただけで十分。口説かれるのはうれしいけれど、何かあの頃の思い出までも壊れてしまいそうでやだなー。まさか、そんなつもりで一緒にいたの?」。
そんなつもりも何も、世の多くの男達はそうである。しかも、盛んにシグナルを送っていたのはそっちだ。
そのとき、彼女の携帯が古い映画のメロディを奏でた。彼女はバッグから探りだすと私のことなど気にせず喋り出した。確か、「男と女」という映画だったと思う。
やがて電話が終わると、
「ごめん、これから予定入っちゃった。ここは私がおごるから」。
と、私の手から会計伝票をもぎ取り、さっさと勘定を済ませてしまった。
「また電話してよ。明日でも良いし」。
そう言って小さく手を振ると、さっきの眠気はどこへやら、彼女は急いで店を出て行った。
カウンター越しのマスターの視線が痛い。
「(明日は東京に帰るんだよ)」。
全てが一気に萎えた。
彼女がいまだに独身なのは、厄年のためでなく、「片思いがお似合い」なわけでもなく、無意識のうちにこんなはぐらかしを男にかましてしまうからに違いない。彼女はこのことに気が付いていないようだ。
彼女に電話をして来た相手が女性なのか、男性なのか、そんなことを気にしてもしょうがない。
けど、恋がしたくなった。自分も片思いがしたくなった。
そしてまた、来年も「片桐恭子」に会いたくなった。
− 完 −
(もちろん、フィクション)
(秀)
-
前の記事
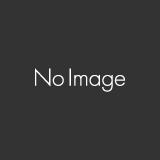
第559話 ■片思いの美学(4) 2001.07.30
-
次の記事
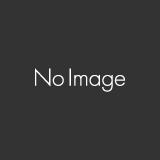
第561話 ■暑中お見舞い 2001.08.01