第742話 ■近未来事件簿・クローン人間殺人事件
203X年。ショッキングな事件が起こった。出生時に双子のクローン人間として誕生した一方がもう一方を刺殺するという事件だ。自分のクローンとは言え、別の生命体としての人間を殺したわけだから普通に殺人罪を適用すれば良いようだが、犯人の動機や供述を知るにつれて、ことが単純でないことに改めて気づく。
犯人の供述から洩れ聞こえてくるのは、
「あいつのせいで、俺はいつも半人前の扱いをされていた」
「おれはあいつの存在なんか認めちゃいない」
「あいつは俺のクローンなんだ。俺は自分のクローンなんかいらない。だから殺った」
「俺があいつを殺らなければ、俺があいつに殺られていたに違いない」
というものだった。
やはり普通の双子とは感覚が大いに違っている。クローン双子の全てがこのような感情を持っているとは限らないが、一旦相手に憎悪の感情が芽生えると、同じように相手も自分に対してそういう感情を持っていると判断してしまうのはクローン双子に特有なことだろう。また自分が望みもしなかった自分のクローン人間が存在するというのも、その憎悪のきっかけになるのかもしれない。ただ、犯人が勘違いしているのは、クローン双子の場合、受精後母胎に着床してから後は、自分がクローンなのか、相手がクローンなのかは誰にも分からないはずだということだ。
そしていよいよこの事件に対する初公判が東京地裁で行われた。検察は当初の方針通り殺人罪を適用し、彼(太郎:仮名)を起訴した。多くの人々の関心は、自分が望みもしなかった自分のクローン人間の存在を抹消することに対して裁判官が何と言及し、情状が酌量されるものかという点であった。
ことは裁判の冒頭に起きた。裁判官の人定尋問に対し被告の太郎は「自分は(殺害された)次郎(仮名)だ」と言った。場内がざわついた。検察は次郎を殺害した犯人として太郎を起訴した。刑事訴訟法上、被害者と犯人を特定しなくてはならない。これが犯人の偽証で、裁判の混乱を狙ったものだとしても、彼が太郎であるのか次郎であるのかを断定する科学的な手がかりは何もない。クローン人間の一方が殺された事実は明白だが、姿形、指紋もDNAも同一である両者の事件を裁くことは冒頭からつまずいてしまった。法律の盲点はここにもあった。
— この話はフィクションです。—
(秀)
-
前の記事
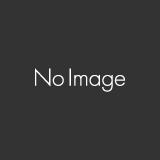
第741話 ■おやつの引き出し 2002.04.19
-
次の記事
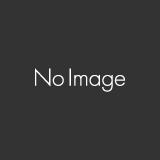
第743話 ■アースコンシャスを斬る 2002.04.23