第951話 ■バリバリマシン
大学4年のときの12月。小学校、中学校と同じ学校に通っていた友達にコンビニでふと出会った。たまたまいつも通っているコンビニとは別のコンビニで出会った。家はそれほど離れていないながら、高校が別になってからは生活のテリトリーが違うため、会ったのは随分久しぶりだった。彼は「ちょうど良い所で会った。今度、写真撮りに来てくれ!(原文は方言)」と私に頼む。よくよく話を聞くと、バイクで走っているところの写真を撮ってくれとの依頼である。中学生のとき、私は学校一の写真少年だった。
その足で彼の家に行ったのか、日を改めて彼の家を訪ねたかははっきり覚えていない(多分前者だったと思う)が、彼の家で更に詳しい話を聞くことになった。久しぶりに入る彼の部屋の壁にはライダースーツ(バイクの皮ツナギ)が吊るされていた。中学を卒業してからほとんど会っていなかったので、彼がオートバイ好きになっていたとは知らなかった。そして雑誌を取り出し、「この雑誌に写真を投稿したいから写真を撮ってくれ!」という依頼だった。
その雑誌の名は「バリバリマシン」、略称「バリマ」。オートバイの走り屋の雑誌だ。この場合の走り屋というのは暴走族ではない。峠のコーナーなどを攻め、そのテクニックを楽しむ類である。ツーリングなんてのもやらない。このためバイクも中型で2ストロークエンジンがほとんどだ。雑誌にはそんな走り屋の読者からの投稿写真が掲載され、読者間ではこれがバイブルであり、この雑誌に写真が載ることがステータスになっていた。中にはマシンを大きく傾け、地面との摩擦で膝から火花を散らしているものもある。ライダースーツの膝の部分にはパッドが付いていて、彼のそれも擦れている。但し、火花を散らすためには、そこにジュースの空き缶をガムテープで貼り付け、それを地面に擦りつけるのだと彼は言った。
早速次の日曜日、彼のバイクの後を車で追いかけ、その峠に向かった。当日集まったそのグループのライダーは10人を超えていた。カメラマンを連れてくるという情報が回っていたせいか、いつもより多いらしい。中には私のバイト先のガソリンスタンドのお客さんもいた。別に怖い人の集まりではないが、自分にこのような趣味がないため、そんな人たちの中にポツンといる環境は初めてのことだった。ふと垣間見た異次元のようだ。
車体を内側に傾けるコーナーの内側で待って、流し撮りで何枚もシャッターを押した。バイクの後ろに乗せてもらって、追尾しながらの撮影に挑戦してみたが、手が自由にならないのでダメ。それならと、車の助手席から追尾しながら撮影は構えることはできるが、望遠レンズのため、揺れ幅が大きく、ピントを合わせている間に酔ってしまって、これまたダメだった。それなりに写真は気に入ってもらったが、実際にバリマに投稿したという話はとうとう聞かなかった。もはや彼ももう峠を攻めるような走りはやっていないだろう。
(秀)
-
前の記事
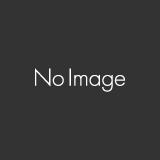
第950話 ■トニー谷って? 2003.02.25
-
次の記事
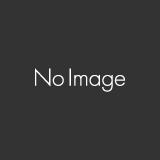
第952話 ■老人マーケット 2003.02.27