第440話 ■銭湯
- 2001.02.07
- コラム
かつて、中学生の頃まで銭湯通いをしていた。徒歩一分の所に銭湯があり、この他にも徒歩圏にもう一軒の銭湯があった。かつては町内にうるさいオヤジというのがいて、私の父親もその一人だった。騒ぐと怒られるし、浴槽の中をぬるくしても怒られた。そして、友達と行って、なかなかあがって来ないと兄が迎えに来て、これまた怒られた。
銭湯には色々な人がやって来る。誰かれとなく話し掛けて来る人、裸で四股を踏む人、オカマもいれば、刺青の人もいる。貧乏人も金持ちも区別のない裸同士の社交場だ(とは言うものの、金持ちはまず来ない)。暗黙のうちに宣戦布告無く、熱い湯船につかったまま、「あいつには負けないぞ」と、我慢比べをしている人もいる。こんな場合は、いずれか一方が湯船あがると、もう一方も即座に、しかし勝ち誇ったようにあがるのですぐに分かる。風呂からあがって、牛乳を飲むなら腰に手をあてて飲むのが作法。できればフルーツ牛乳が良い。そして、今の私なら真っ先にマッサージ椅子(有料:当時一〇円)に腰を下ろすことだろう。
この銭湯、元旦は早朝六時からの営業であった。しかも、営業時間が短いのでとても混んでいる。毎回この元旦の「一番風呂」を気持ち的には目指してみるものの、いつも早々と自分だけ朝風呂を浴びて来た父親に起こされる。父が早く起きるのは年にこの日ぐらいしかない。翌日はお風呂屋さんが休みになるため、この日ばかりは何とか一〇時(午前)の営業時間までに駆け込まなければならない。まさに正月にふさわしい、非日常的な行事だ。家に帰ると、新しい服が並べられていた。うれしい。
私は年に一度のこの朝風呂の習慣を今も受け継いでいる。今では自宅の小さな浴槽ではあるが、かつては味わえなかったのんびりした雰囲気で新年の朝を迎えることにしている。親父もきっとそうしているに違いない。
(秀)
-
前の記事
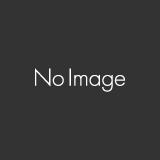
第439話 ■変なじいさん 後編 2001.02.06
-
次の記事
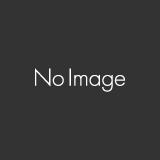
第441話 ■懐具合 2001.02.08